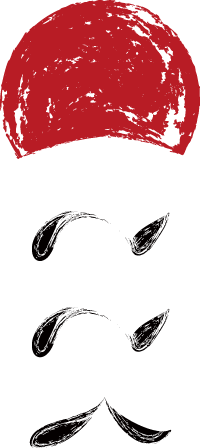一年前ぐらいにテレビの取材に協力してくれた農家さんが、自分で栽培したマンゴーを届けてくれた。ディレクターのHさんに渡してくれと言う。
最初電話でHさんの名前を言われ、はて、一体誰のことを言っているのか、なかなか思い出せなかった私。
取材の時、たぶん挨拶程度に「マンゴーができたら買いに行きます」と言うようなことを言ったのだと思う。その言葉、名前、約束を、彼はきちんと覚えていた。
最初は「テレビに出るなんて夜も寝れなくなる」と断られたものの、みんなで説得の上で出てくれた。あんなに嫌ががっていた彼が、テレビに出ることを親戚中どころか農協の職員にまで告知していてビックリした。
そのぐらい、彼にとってはすごいイベントだった。
そんな気持ちが、今日立派なマンゴーで帰ってきた。
心が美しすぎて涙が出る。忘れていた自分が憎らしい。
このマンゴー、どんな味がするんだろう。
必ず、Hさんに届けます。
#大切なこと
5月18日、ここくは12周年を迎えます。
この12年を思い起こせば…
購入したトラクターが2ヶ月で廃車になったり
麦を徹夜で釜で収穫したり
コンバインが曲がらなくなったり
4トントラックで小川に落ちそうになったり
無視され続けたり
船で沈没しそうになったり
熱中症になったり
乾燥機を掃除していてアバラを折ったり
騙されたり
裏切られたり
怒られたり
いじめられたり
…私個人はいろんなことがあって何度も挫けそうになりましたが、ここまでやってこれたのはなぜなのか。
きっと、ここくは強いからだと思います。
ここくは私一人ではなく、作る人⇄売る人⇄買う人の関係性。一人じゃないから強いのです。全てのここくに関わる人の手によって、ここくは12周年を迎えます。
横浜でデザイナーだった私は、東日本大震災より前に宮崎に移住して農業をすることを決めていました。
ありとあらゆるお店の棚から食料がなくなったあの震災の夜、食べることができないお金しか持っていなかった自分が情けなくなり、「自給自足」の夢を見ました。
しかし実際に畑や田んぼをやってわかったのは、それはめちゃくちゃ個人主義の都会的な考え方だったこと。一人でできることなんて本当に少ししかなくて、たくさんの人にお世話になりながら生きていることを知りました。
個と個がもっと近づくように。
「ここく」にはそんな意味も込められています。
その個と個を結ぶのは、安さでもなく、見た目の良さでもなく、栄養成分でもない。お話から産まれる「おいしさ」です。
おいしいおはなし届けます。滋味はこころの豊かさに。
DELIVERING TALES OF DELICIOUSNESS
WHOLESOME FLAVOURS WHOLE HEARTEDLY
この想いだけは、これまでもこれからもずっと変わりません。
楽しいことも辛いことも、全てみんなで味わえる。
だから楽しい。だからおいしい。
12周年にあやかり、オンラインショップではあれもこれも感謝を込めて12%オフ!このセール、いつまでやるかは在庫次第です。
しばらく一緒にここくを楽しんでもらえたらと思います。
#大切なこと
価格改定のお知らせです。
10年間、ほとんど値上げすることなく同じ値段で踏ん張ってきましたが、ここ数年の原油価格の高騰、それに伴い包装資材があがり、米代もあがり、輸送費もあがり、そして人件費までもあがりました。なかでもお味噌はほとんど利益がない状態が続いてきました。
「プレミアム味噌にはしたくない」という想いから、もともと内容の割に高くない金額設定を10年貫いてきましたが、さすがに赤字になると潰れてしまうので今年から値上げをすることを決断しました。
みなさん厳しい状況と思いますが、どうかご理解・ご容赦のほどよろしくお願い致します。
これからもおいしいものをお届けしながら、大切な種をしっかりと次の世代へ繋げられるように精進してまいります。
#大切なこと
今日お店に来られたお客さんに
「昔〇〇園芸で出店されてましたよね?その時に麦茶を買っておいしくて、ずっと気になってました」
と言われ、涙腺が刺激されている自分がいました。
だってそれ、、、もう10年ぐらい前の話です。
まだその時は初めての麦の収穫を終えたばかりで、麦茶とごはん麦しか商品なくて、、
お客さんて、そんな昔に買った麦茶のことをまだ覚えていてくれてるものなんですか。
その時に隣に出店していた平田くんが塩を売っていて、その塩が美味しかったからそのあと平田くんの塩で味噌を作るようになって…(結局平田くんはやめてしまったので自分で作るハメになりましたが^_^;)
だから私にとっては忘れられない出店。
記憶の奥の方に大切にしまい込んでいた時間。
それをお客さんと共有してるなんて思ってもなかった。
いろんなイベントでいろんな方に出会います。私はいろんな人に会うのが好きです(写真は先日の糸島での発酵フェス)。
一期一会な感じも素敵だけど、きっとすぐに忘れられるんだろうと思って寂しい気持ちもあり。
涙腺が刺激されたのは、嬉しくてなのか、その頃の苦労を思い出してなのか。あぁ、あんなショボかった出店でも覚えていてくれるんだ、忘れられてないんだってのが一番大きいのかもしれない。
たくさんの方に支えられて今がある。
まだまだ途上にいますが、どうかここくと出会ったこと、忘れないでいてください。そしてまたお会いできた時はぜひお声がけくださいね。
またお会いできるのを楽しみに。
いつもありがとうございます。
#大切なこと
大粒の青大豆を道の駅で買い、育てはじめたのはかれこれ12年前。
2年育ててみたけれど、どうもうまく育たない。
お向かいのおばちゃんにタネを預け、自分は育てるのをやめた。
それから3年後、「すごいのが取れたとよ!」とおばちゃんが持ってきたのは小粒の青大豆。品種改良された青大豆が、おばちゃんが自家採種を繰り返すうちに先祖返りしたらしい。
その数株から丁寧にタネを取り出し、本来の小粒大豆だけになるよう毎年植えてきた。
でもなぜか、青大豆ばかり猪にぐちゃぐちゃにされてしまう。
…そして昨年はついに全滅。
今年は仕方がないので一昨年のタネを撒いたところ、やはり発芽率が異常に悪く芽が出たのは5%ほど(1枚目)
大豆が光を遮らない丸裸の畑は、夏の日差しの中で草だらけに。(2枚目)
これではいけないと汗まみれで草むしりして、5分の1ぐらいは救助した(3枚目)。今年は畑を変えたせいか、よく育っていた。
しかしやはり、猪に全てぐちゃぐちゃにされてしまう。(4枚目)
結局、実が入っていそうな株だけを数株抜き取り、露草だらけになった畑を草刈機で刈り取り、刈り取った草を全て運び出す(5枚目)。
汗まみれになって、手が豆だらけになって、豆がはぜて痛い想いをして、ふと我にかえる。
一体何してるんだろう
一銭にもならないじゃないか
なぜ獣害を放置するのか
このタネは残るのだろうか
残す意味はあるのだろうか
もう7年、こうして毎年不毛なことをし続けている。
先祖返りにワクワクしたあの頃の気持ちも、無惨に潰される大豆のようにズタボロになっている。
そろそろ決断しなければいけないのかもしれない。
#大切なこと #先祖返り #清武青豆
宮崎では早期米の収穫がほぼほぼ終わりました。
一昨年、10年続けた田んぼをやめてからは、沖の潮を汲み上げるための船を出してくれている方からお米を買っています。※この方はお店の大家さんでもあります。
その田んぼはいつもの通り道にあるから、田植えから稲刈りまでの全ての過程を毎日見させてもらっていて。
田植えしたあと、田車と呼ばれる手押しの機械で除草をして疲れ切っていた姿。今年は田車が途中で壊れてしまい、難儀しました。猪が畦を掘ったり、草刈りをしたり、いろんな景色を毎日見てきました。
知っているからこそありがたいし、おいしいし、心が豊かになる。当たり前にあるものではない食。オートマチックにできあがるものではないことを伝えたい。産業的に作られたものばかり食べていると心がどんどん空っぽになる。一人で生きているなんて思わないでほしい。
わたしが田んぼをしていた時、子供たちにどれだけ伝えられていたかといえば、ほとんど伝えられなかったように思います。どれだけ口で伝えても、現場を見ること以上には伝わらなかった。
家族にも伝えられないほど難しいこと。デザイナーだからできると思って自ら畑に立つことをはじめた農業でしたが、情けないことに1割も伝えられていないと思います。
「8ヶ所の畑、合計で30000平米を1人で管理してます」…なんて言って何が伝わるのか。毎日早起きして草刈りしてるけど、映えない写真をあげるとみんな離れていくからあげられない。
だから私は独りよがりな想いを閉じ込めて、独りよがりに大切に、いただいたお米を噛み締めています。この気持ちはどこへも向かうことなく、毎日の食卓に並んでは家族にも知られることなく消えていく。
無事に終わった稲刈り後の田んぼを見ながら、感謝を独り占めしている私です。
#大切なこと #早期米
畑担当から、食べる担当のみなさまへ!
だいぶ遅くなりましたが、先日、麦の収穫が無事に終わりました。
今年は麦の実が充実するべき4月が梅雨のように毎日雨だったこともあり、日照量が足らず、収穫が大きく遅れてしまいました。
その代わり?梅雨が6月に入った今もいまだに来ないという珍しい現象で、収穫は遅くなりましたがしっかりと余裕を持って収穫も終えることができました。収穫後の乾燥、籾摺り、選別、機械の掃除、畑の耕運、全て終わりホッとしているところです。
今年も無事に、麦茶、ごはん麦、麦味噌、あわせ味噌、大麦粉、たいやきなど、しっかりとお届けできそうです^_^
そんなおつかれさまな一区切りで咲いてくれたのはゴボウの花。
ゴボウは栽培していないですが、こうして毎年花を咲かせては種を落とし、どこかしらに勝手に生えてきます。かれこれ5年はこうして毎年花を眺めているから、もう家族のような存在。
畑に一人でいても寂しくないのは、鳥や虫やウサギなどの動物に加えてしっかり野菜たちが息づいていて、こうして限りなく無垢なメッセージを送ってくれるからでしょう。
ストーリーやリールで、少しでも伝わればいいなと思いながらアップしています。
次は灼熱の中で育てる大豆。種まきの7月下旬まで、しっかりと体調を整えながら準備をしていきたいと思います。寒気の影響でまだ朝晩冷える毎日。あたたかなお味噌汁でどうぞお身体ご自愛ください。
#大切なこと #ゴボウの花
久しぶりの玄米ごはん。食べ盛りの子供たちがいるので普段は白米ですが、米が切れてしまったので備蓄していたいただきものです。
このお米は、これから脱サラして農業をはじめようとしていた方にいただいたもの。
3年前ぐらいにお店に来てくださった時は関東から宮崎への移住を考えていましたが、1年ほど前再び訪れてくれた時、富山の山田町に就農することを決めたと教えてくれました。
山田町といえば牛岳スキー場があり、私は以前そこでスキーのインストラクターをしていたのでよく知っています。あんな山深いところに…!?雪も経験したことがないとおっしゃっていましたから、はたしてこの冬はどう過ごされたのでしょう。
そんな彼がお土産で持ってきてくれた富山の地でとれたお米。
しっかりと噛み締めながら、かつての山田町に思いを馳せる朝ごはん。急に冷え込んだ朝の身体に染み入るごはんでした。
…全国いろんなところで農業をはじめようと頑張っている方がいらっしゃいます。ここくにもたくさんの方が遊びにきてくださいますが、未だに苦労している私の口から出る言葉は楽しくないことばかり。
やる気に満ち溢れている方の背中を押してあげられる人間になりたい気持ちと、人生をかけて挑もうとする姿に適当なことを言えない自分とが交錯していつも自己嫌悪になります。
かつて私も散々言われました。当時は嫌な思いをしましたが、今振り返るとみな嘘は言ってなかった。それぞれの景色で見てきた苦労を伝えてくれていたと分かります。
いつかわかってもらえるその日まで。
ずっと心にかけています。ごちそうさまでした。
#大切なこと #富山 #山田町
このお店を借りてからもう10年経ちました。
以前は地域に愛される酒屋さんでしたが、大型モールの進出などで閉めることになり、このお店の上で畑をしていた私が貸していただくことになりました。
酒屋の店主とは保育園の親父会で知り合ったご縁。
その後、彼は酒屋をやめて釣船を始め、私はここで味噌を作りはじめます。お店を借りてから知ったのは、酒屋なのに厨房があったこと、そしてお母様が地元老舗の醸造所の娘だったこと。
そんなご縁をいただき、私は自分で栽培した麦を持ち込み、麹をつけてもらうことで味噌作りをはじめることができました。
その後、塩も自分で作るようになり、元店主の釣船で沖に出るようになります。やがて同じ父兄でもあった地区の幼馴染が潮職人に加わりました。2人は今、船で沖に出て海水を汲んでいますが、他所者の私が来なければこんなことにはならなかったでしょう。
不思議なご縁はまるで運命であったかのよう。余所者の私をやさしく受け入れてくださったみなさんに感謝しながら、できあがった塩で今日も味噌を仕込んでいます。
これは、私たちの麦味噌に詰まっているたくさんのお話のほんの一部。流通や情報化社会の中で消えてしまわないよう、ここに記します。
#大切なこと #沖の潮 #麦味噌
今年もありがとうございました。
10周年を迎えた2023年でしたが、今年初めて出会ったみなさんも、これまでずっと支えてくださったみなさんにも、たくさん感謝で振り返る一年でした。
まだ「ここく」の名も生まれていない頃、一番最初に出会った数人の1人がこちらの地主さんです。
もう11年になりますが、変わらず畑を貸してくださることに改めて感謝です。この日は大豆の収穫のための草抜きをしているところにひょっこり現れ、少し草抜きを手伝ってくださいました。
たくさんの方に支えられて今があり、そんなみなさんのもとに私たちは畑担当としてずっとおいしいものを届けていきます。
先人たちから受け継いだ種を守りながら、本当の心の豊かさを味わいながら、ずっとこの小さな幸せが子供たちにも続いていくように。
温かでおいしいお味噌汁でしっかり身体を整えながら、どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。
来年もどうぞ宜しくお願い致します。
#大切なこと #10周年
朝露が美しい冬の朝です。
キラキラした朝の野良周りには、
待ちに待った光景が拡がっていました。
緑色のラインが見える!
10日前に蒔いた麦の種、しっかりと芽吹いていました。
毎年毎年、この瞬間が来るまでは心配が尽きず、雨の日でも土を掘りタネの状態を確認していたほどです。
5月の黄金色の麦畑へ続く景色の始まり。
椎葉村のおばあちゃんに譲っていただいたこの麦も、この子達で11代目になります。
今年もしっかりお世話をして、しっかり次に繋げていきます。
今年も残すところ半月ほどになりました。
忙しい中でもしっかりと地に足をつけ、大切なことを見失わないようにしたいと思います。
#麦畑 #在来種 #自然栽培 #大切なこと
先日畑の草刈りをしていた時、見慣れない大型スクーターがやってきました。農家以外は来ない場所だから、見慣れない人はすぐに分かるのです。
歳のころ60過ぎの叔父様が、バイクを止めてなんだかこっちを見ています。
誰?
地主…ではないし、、地区の人?
何かまた文句を言われるような嫌な予感をしつつ無視していると、なんとバイクを止めて近づいてきました。
ああ、これまた厄介案件だ。何も悪いことしてないのに。。今度はなんだろう…草刈り機は危ないのでエンジン止めて笑顔で挨拶。
何をいうのかと思いきや
「これはいくら貰えるんですか?」
「はぁ?」
「役場の方ですか?」
「え?違いますけど…」
…なんでも(おそらく定年して)バイクで色んなところを見て周ってるんだそうで、よく見かける草刈りの人がどこに雇われてるのか知りたかったんだと。
この草刈りやらないといけない集落の無言の圧力を知らないんですね。私しゃこの畑を借りてるだけの人間です。やらないと周りに迷惑かけるし…(云々カンヌン)お金もらえるならもらいたいですわ〜とひとしきり説明すると、社会見学を終えた子供のように納得して帰って行きました。
あまりに知られていない農家の実情。自分たちの食べているものがどうやって育つのか、どんな人がどんな思いで…以前の部分すら知られていないのかと驚きました。
彼は私の話を聞いて何を納得して何を持ち帰ったのだろうか。
さらにその時、この写真のうちの大豆畑を見て「でもここは何も育ててないですよね?」と言われまして。
ああ本当、草だらけですものね。何も言い返す気になれず苦笑いをして、寂しい気持ちをしまいこみました。
ようやく冬らしい冷たい風が吹くようになり、そんな大豆畑もそろそろ収穫に入れそうです。畑担当からのご報告でした。
#大豆畑 #大切なこと #草刈り #農業
種を譲り受けて11代目の麻尻大豆。実がだいぶ太ってきました。10月に入り、ありがたいことに晴天が続いています。
高千穂のシンイチさんから譲り受けた極小の黄大豆、麻尻大豆。「キロいくら」と、重量で取引される大豆にあって、こんな小さな大豆で生業とすること自体、無謀なことだと思います。
在来種と呼ばれる大豆は日本全国あるものの、改良品種はみんな大粒にされていることもあり、見た目では在来種かどうかあまり判別がつきません。
改良品種を自家採種で育て続けて、「地大豆」として売られていることもあります。
そんな中で、この麻尻大豆はもう一目で在来種とわかる小ささ!形も少し扁平な形で「味噌や醤油にするとおいしい」と、地元の方の太鼓判もあり惚れ込んでしまいました。
粒が小さいだけでなく、野生に近いのか背が高くなって必ずと言っていいほど倒れます。収穫は困難を極め、選別も大粒用に開発された大豆選別機は役に立ちません。
この大豆に合う機械を探し回り、ようやく手に入れましたが、やはり最後は手選別。未だに全てバットに広げ、目視で悪い大豆を取り除いています。
そこまでするのはやっぱりこの大豆が好きで、後世に残していきたいから。
種は誰のものでもありません。
先代からずっと繋がれてきた奇跡のような命の連鎖を、たまたま私が預かっているだけ。次の世代にきちんと受け渡すために、おいしいお味噌や醤油としてみなさんにお届けしています。
そしてこれを受け取ってくれる方がいるからこそ、11年間預かり続けてこれました。みんなで守っている種。私は畑担当としてこの大豆を見守っています。
#大切なこと #在来種 #麻尻大豆 #無農薬 #無肥料 #自然栽培
伝わる・伝わらない
デザインの仕事についてからはもう25年、農業を始めてからはもう10年。いったいどれだけこの言葉を使ってきたことでしょう。
伝えたいことは沢山あるけれど、実際ほとんど伝わっていない。冷静に考えれば分かるのに、気づくと「伝わってる」ことにしている私がいます。
真夏の大豆のお世話の大変さをどれだけ伝えても、そもそも大豆がいつどうやって、どんな形をしているのか?そこからはじめなければならなかったり
黄金色に揺れる麦の穂の美しさを伝えたくても、スマホの小さな画面の中で満足されてしまうもどかしさだったり
圧倒的な質量で迫ってくる海の美しさと怖さ、その時感じる人の小ささと愛しさは、やはりウネリの海に出ないと味わえないことであり
そんな畑と海の景色が混じり合う、味噌や醤油などの発酵食品は、もう感動的に凝縮されすぎて、何から話せばいいのかすらわからないわけで
かといって「諦めたらそこで終わり」だから「1%でも伝われば」と思いなおしたり、もう何年もそんな行ったり来たりを繰り返しています。
食べものの向こうに広がる豊かな景色。それを感じることで、情報では得られない豊かさを感じてもらえたらいいんだけどなぁ
かつて都会で虚無感を抱えながら過ごしていた自分に届けたいのかもしれません。
明日、日曜日の15時から、お店でゆるーくインスタライブをしたいと思います。どうなるか分かりませんが、お時間のある方は見てみてくださいね。
#インスタライブ #大切なこと
「中耕」は「ちゅうこう」と読みますが、そのまま畝の間を耕す作業のことです。
大豆の中耕作業は真夏の炎天下で行われる、一年の中でもっとも過酷な作業のひとつ。
その様子はこれまでみなさんにお伝えすることはできませんでした。一人ですし、とても写真を撮る心の余裕はないからです。
そんな念願がかなったこの写真。
別プロジェクトでわざわざ東京から来てくださったカメラマンさん @kenshimi2002に撮っていただきました。
「無農薬」の言葉の向こうにあるのはこんな風景です。
もっと畝幅を狭くして除草剤を撒けば、たくさんとれるし管理も楽ちん。
それをすることなく、こうして機械で土を草の芽にかぶせることで除草剤の代わりにしています。労力もかかるし沢山はとれません。
「無農薬がいいけど、高いのよね…」って、よく聞くし僕も言いそうになる時があります。
それは単に安いものと比べて言っているにすぎないのですが、実際に作業している人間には「あなたの作業にそんな価値はないわ」と言われているようで、心に何かグサリと刺されたような気持ちになります。
買う側はできあがったものしか見ていないし、こんな過程も伝えていないから無理もないことなんですけれど、、
無農薬でがんばろうとはじめる方はたくさんいますが、みんなからそうして心をグサグサ刺されながら、もう刺されたくないから普通のものと同じ値段にしてしまい、結局続けられずやめてしまう。
もう何度も見てきました。私にできることはなんだろうと、いつも考えます。
#大豆 #無農薬 #無肥料 #自然栽培 #在来種 #麻尻大豆 #大切なこと
何かに追われていると見えないもの。
夕暮れ時に突然はじめた庭の草むしり。庭にしゃがんで初めて、苔が一斉に芽を伸ばしていることに気がつきました。
いろいろなものが芽吹き、実りへと向かう春です。明日から慣れない環境で新しい生活が始まる方もたくさんいることでしょう。
忙しい毎日の中で自分を見失いそうになる時は、あえて全てを放り出して自然に触れてほしいものです。
いつも素通りしていた景色が見えるようになるだけでなく、自分の心の声を聞くことができますよ。
まだまだ冷え込みますのでどうかお身体ご自愛ください。
#大切なこと
まるで切り絵の中に迷い込んだような、風のない朝の畑から。
ビルもなく、電線もなく、空だけが果てしなく広がっているこの風景を、もっとたくさんの方に見てもらいたい。知ってもらいたい。
ここには人もいなければ情報もなく、安全だとか安心だとか、農薬だとか添加物だとか、頭を抱えてしまうような難しいことは何にもなくて。
いつも色々言ってるけれど、本当はこの風景を感じてもらえたらそれでよかったりもします。
茂みで眠るアナグマや野うさぎと同じように、私達は鼓動とともに生きていること。
オーガニックな選択の前に、まずは自分がオーガニックな存在だってちゃんと確認すること。
ここにいろんな人が来て、言葉では伝わらないことを感じてもらえるように。
少しずつ、ここくは前進していきます。どうぞお楽しみに。
#オーガニック #大切なこと #キャンプ #畑泊
昨年末のいい報告。
倉庫を立てた場所は9年前に購入した畑ですが、その両隣の二つの畑はずっと何も作っていませんでした。
倉庫の目の前なのでぜひ借りたかったのですが、ずっと貸してもらえず。理由は簡単に言えば余所者だから。最初のちょっとしたボタンの掛け違いでの誤解もありました。
結局9年間、耕すだけで何も作らない年月が流れましたが、先日跡を継いだ息子さんから貸していただけることになったのです。
9年…もう完全に諦めていたので不思議な気分。時間はかかるけれど、時間が解決してくれるとも言えます。
そんな私の奮闘ぶりをずっと見てきた畦の野良大根。一株だけ気の早い花を咲かせてお祝いしてくれているように見えました。
#大切なこと #米良大根 #在来種 #余所者 #新規就農 #野菜の花
終わったよー!
残り3枚の畑で大豆を刈り終えることができました。もちろん親方…汎用コンバインのおかげです(デカくて頼もしいので親方とこれから呼びます^_^)
去年の今頃は、収穫作業をしながら汗まみれ埃まみれでクラウドファンディングのことを考えていました。
1000万円なんて夢物語
…でもやらなくては何も始まらないし、体壊して終わってしまうよりずっといい…集まらなくてもいいから、やろうよ
そして映像ができて
年末に募集がはじまって
それに応えてくれたみなさんがいて
同じ想いの方が集まって
勇気や感動をたくさんもらって
本当にコンバインが現れて
…そんな一年を経て、今日があります。
こんな感動的な一年になったのはその前に認定農業者になれたからで、そうなれたのは積み重ねてきた7年の実績があったからで…
遡れば、ずっと積み重ねてきたからこそ、今があるんですね。そしてこれからも積み重なっていく壮大な「おはなし」
古代から紡がれてきた種とともに、次の世代へ紡いでいきましょう。私は畑担当で引き続きがんばります。
おいしいおはなし、これからもたーくさん届けます。滋味は心の豊かさに。
Delivering Tales of Deliciousness
Wholesome Flavours Whole Heartedly
#クラウドファンディング #大切なこと #麻尻大豆 #沖の潮 #在来種 #自然栽培 #発酵 #発酵ライフ #熟成 #酵素 #酵母 #腸活 #菌活