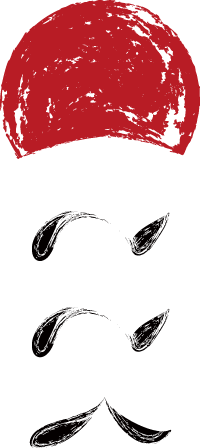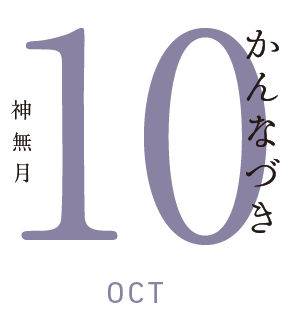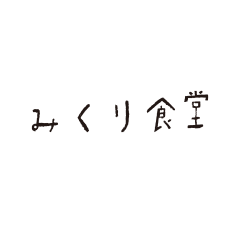
12:30




15:30
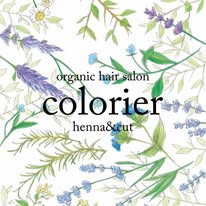
15:30

14:30〜
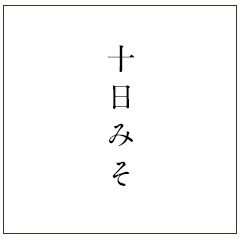
味噌=お味噌汁、というのは間違いではないですが、時間がなかったり、一人暮らしだとなかなかお味噌汁も作らなかったりするものです。
そんな方でも手軽に発酵食品を、ということで作ってみたのがフムスみそ。
じっくり煮込んだひよこ豆をペーストにして、ガーリックやレモン汁、クミンであえて、オリーブオイルと食べる東欧料理のフムスが大好きな方も多いはず。
あのナッツのような風味のひよこ豆を、甘みのある米糀で熟成したら果たしてどうなるのか。いわば東欧と東洋のコラボレーションです。
まったくクセのないフムスみそは、ひよこ豆独特の匂いも消えて、チーズのような旨味ペーストになりました。
やっぱりオリーブオイルとの相性が抜群なので、お水で溶いてサラダにかけ、オリーブオイルをひとまわし。ヘルシーなみそドレッシングになります。砕いたカシューナッツを散らしても◎
パスタはミルクパスタがおすすめ。
少し硬めに茹でたパスタに豆乳などを入れ、別で炒めておいたきのこやほうれん草の具材と混ぜ合わせながら和えればできあがり。仕上げに粗挽きブラックペパーを入れるとカルボナーラのようにもなります。
まるでたっぷりのチーズを食べているみたいに濃厚なのに、チーズじゃなくて味噌!っていうのが最高です。
他にもパンやカンパーニュに薄く塗り、サラダなどをのせてオリーブオイルで食べるのもオススメ。ディップで食べるのももちろん美味しいです。
毎日味噌汁もいいですが、たまにこうして洋風で味噌を食べるのが味噌を欠かさず食べる発酵生活のコツ。
是非いろんな味噌を使い分けて楽しんでもらえたらと思います。
#発酵生活 #フムス #フムスみそ #沖の潮 #米糀 #ほうれん草とキノコのクリームパスタ
赤味噌、白味噌の違いは実は熟成期間の違いでしかありません。
麦味噌も米味噌も、一定の熟成期間が過ぎると甘みと香りが落ちていき、代わりにコクが生まれていきます。
九州が短期熟成の麦味噌なのは甘味と香りを大切にするから。
関東が長期熟成された米味噌しかないのは、麦の香りは期待せず、コクを重視するからです。そのため、長期熟成の麦味噌というのはあまり見かけることがありません。
そこで、ここくの麦味噌を長期熟成するとどうなるのか。
今年初めての試みでしたが、コクがしっかりあるのに辛くない、体に旨みが染み渡るまろやかなお味噌になりました。
このコクのある赤味噌と、香り高い麦味噌を調合してもいいものです。実はこれが関東でいう「合わせ味噌」。九州でのそれは、コクよりも米の甘味を期待しているので、仕込みから米糀と麦麹を合わせてしまう合わせ味噌なんです。
そんな合わせ味噌も昨年初めて造りました。
米:麦=1:1で仕込んでいるから(通常は8:2ぐらい)麦の香りも米の甘味も楽しめるのがここくの合わせ味噌の特徴です。
台風の被害でストップしていたこの合わせ味噌もようやく目処が立ち、11月中旬から樽を開けようと思っています。
それらに比べてクセのないフムス味噌はひよこ豆の旨味と米糀の甘味が凝縮された旨味ペースト。オリーブオイルやナッツ類と相性抜群で、サラダやパスタなどに使える発酵調味料として重宝します。
これら4種の味噌から選べる、今年の歳末セット。
超早割の受付は今月末までとさせていただきます。
身体を優しく温める冬の滋養にぜひご活用ください。
#滋養 #調味料はいいものを #お歳暮 #超早割
「潮を炊く薪はどうしてるんですか?」と、よく聞かれます。
1番多いのはこんな廃材をもらったりすること。細かく切って薪にしたり、釜にくべられる大きさにして保管しておくのもなかなか大変な作業です。
薪がないと困りますが「薪が欲しい」とひとたび口にすると、みんな大量に木を持ってくるので大変なことに(苦笑 だからあまり言わないようにしています。
ここくの塩窯ができてから、この潮づくり職人のテツヤさんが1人で塩作りをするようになりました。最初はたくさん喧嘩しましたが、今は本当に頼りにしています。
そして頼りにしているからこそ、本気で後継者を探しています。この沖の潮がなくなってしまったら…ここくの心臓部分がなくなってしまうことでもあります。
潮造り職人になりたい方いませんか?潮づくりの方法はテツヤさんが教えてくれます。作った潮はここくが全て買い取ります。都会から移住を考えている方も大歓迎。
詳しい話を聞きたい方はお気軽にご連絡ください。
続けていくこと、ここくはいつも真剣に考えています。
#沖の潮 #後継者 #地方移住 #宮崎
地主さんの庭に生えているのを偶然見つけた、極小の黒大豆「おやし豆」。北海道にある「黒千石」とはまた違い、少し平べったい形をしています。
この黒大豆を焙煎し、きなこの風味を出した黒豆茶。
とっても甘く、味わい深い味が心を落ち着かせてくれます。
出涸らしはまたお料理に使えて便利。
やわらかいので食べながら飲むのもおすすめです。
残ったものはサラダやごはんと炊いてもいいですね。
熱湯を注ぐだけでも味が出ますが、5分ぐらい煮出すとなお味がよく出ます。
1リットルに対して大さじ1〜2ぐらい。お好みでどうぞ。
たべる黒豆茶 130g
原材料:在来極小黒大豆(宮崎産)
賞味期限:1年
#おやし豆
昨日ホキさんでのみそづくり、みそホキにご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。
ゆっくりした時間の中で、のどかな時間をありがとうございました。
後半の座学は質問が飛び交い、ついつい喋りすぎて3時間ぐらい。もう喉カラカラです。最近こんなのばかり(苦笑
有意義な時間にするため、質問してもらえるのはすごく嬉しいですね。
今日は博多阪急うまか研究所にてみそづくりです。
どんな会になるのかとっても楽しみです!
宮崎で行う11月10日(金)、12月10日(日)の十日みその会も受付中ですよ。そろそろ年末の足音が聞こえてきそうです。この機会にぜひどうぞ。
---
11月10日(金)、12月10日(日)
13時から14時過ぎ
・麦味噌2.5キロ 仕込み 3,980円
・みんなでワイワイみそを詰めるだけ
・初めての方のみ14時半から座学 +1,000円
・場所:ここくショップ(清武町船引)
・容器込みの場合+220円
<みそ講座>14:30〜15:30
※初めての方向け
お味噌をはじめて仕込む方に受けていただいています。カビの見分け方、処理の仕方の他、大豆、麦、塩、すべて自社生産だから話せる内容の濃いみそ講座。市販のお味噌の表示のからくりや、自分で仕込む味噌との違いなど、「えっ!そうなの!?」というお味噌の話をたくさんお伝えしています。味噌について詳しくなれるほか、お料理で味噌を使い分けられるようになりますよ
ここく/発酵スイーツ研究所
〒889-1604 宮崎県宮崎市清武町船引3996−1
https://goo.gl/maps/am6hmyHCEZ32
ご希望の方はDMで人数とご連絡先をお知らせください。
#麦味噌 #フムス味噌 #塩麹 #潮麹 #はじめてのみそづくりセット #十日みその会 #麻尻大豆 #沖の潮 #在来種 #自然栽培 #発酵 #発酵ライフ #熟成 #酵素 #酵母 #腸活 #菌活 #調味料は良いものを
左から在来種のここくのごはん麦、まんなかがよく見かけるもち麦、1番右は押麦。
「昔はみんな育てていた」と口々に話す、消えてしまいそうだった麦は1番左の小さな麦。ナビにも出ないような椎葉村の山奥に住むおばあちゃんが、庭先にまだ蒔き続けてくれていた貴重な麦です。ちょうど11年前、偶然出会うことができました。
改良されていない本来の麦は黄色です。真ん中のもち麦は色が白く、さらに大粒になるように品種改良されていて、なおかつ沢山表皮を削っているから白くなります。
もし私たちの小さな麦をこのぐらい白くなるまで削ると、削りすぎでまんまるになってしまいます^_^;
やっぱり麦もキロ単位で取引されるから、粒が大きい方があがりが大きい。次第にみんな改良品種を作るようになり、先人たちが脈々と受け継いできた麦は姿を消しそうになっていました。
在来種のごはん麦は粒が小さく5分付きだから、歯ごたえがとても心地よく、小さいから食べやすいんです。麦味噌も、このごはん麦に麹を付けて仕込んでいます。
ちなみに1番右の押麦はローラーで潰したもの。以前はよく見かけましたが、最近は押し潰していない「丸麦」の方が人気で姿を見かけなくなってきました。押麦の方が麹を作りやすいので、麹屋さんによってはこの押麦でないと麹をつけてくれないところも多いです。
私たちが在来種を育てるのは、その受け継がれてきた歴史に感謝して「いただきます」と手を合わせることに本当のおいしさがあると思っているから。
実際、味もプチプチ美味しいですが、感謝とともに味わう方が生きている感じがするものです。
白米の10倍食物繊維が含まれていて、ミネラルも豊富なここくのごはん麦。ロングセラーの定番商品となっています。
#ごはん麦 #在来種 #自然栽培 #椎葉村
種を譲り受けて11代目の麻尻大豆。実がだいぶ太ってきました。10月に入り、ありがたいことに晴天が続いています。
高千穂のシンイチさんから譲り受けた極小の黄大豆、麻尻大豆。「キロいくら」と、重量で取引される大豆にあって、こんな小さな大豆で生業とすること自体、無謀なことだと思います。
在来種と呼ばれる大豆は日本全国あるものの、改良品種はみんな大粒にされていることもあり、見た目では在来種かどうかあまり判別がつきません。
改良品種を自家採種で育て続けて、「地大豆」として売られていることもあります。
そんな中で、この麻尻大豆はもう一目で在来種とわかる小ささ!形も少し扁平な形で「味噌や醤油にするとおいしい」と、地元の方の太鼓判もあり惚れ込んでしまいました。
粒が小さいだけでなく、野生に近いのか背が高くなって必ずと言っていいほど倒れます。収穫は困難を極め、選別も大粒用に開発された大豆選別機は役に立ちません。
この大豆に合う機械を探し回り、ようやく手に入れましたが、やはり最後は手選別。未だに全てバットに広げ、目視で悪い大豆を取り除いています。
そこまでするのはやっぱりこの大豆が好きで、後世に残していきたいから。
種は誰のものでもありません。
先代からずっと繋がれてきた奇跡のような命の連鎖を、たまたま私が預かっているだけ。次の世代にきちんと受け渡すために、おいしいお味噌や醤油としてみなさんにお届けしています。
そしてこれを受け取ってくれる方がいるからこそ、11年間預かり続けてこれました。みんなで守っている種。私は畑担当としてこの大豆を見守っています。
#大切なこと #在来種 #麻尻大豆 #無農薬 #無肥料 #自然栽培
本当は見せたくないけれど、これが今年の大豆畑。草だらけ!
原因は種まき直後の大雨、そして降り続く長雨です。
こんな時、農家は「あの時あれをしていれば…」と自分の落ち度をつい考えてしまいます。だからこんな状態の畑は自分の未熟さを晒すようで、本当は恥ずかしい、見られたくない。
でも見せなかったら何も伝わらないと思うんです。いつも整然と綺麗に管理された畑しか見せていなかったら、それが当たり前だと思われてしまうから。
月と畑の暦をお使いの方は、今月の写真とぜひ見比べてみてくださいね。
11月の収穫時には枯れる草が大半ですが、枯れない草もあるので、、今時分から広大な畑の草むしりをしています。
まるまる太った良い大豆が沢山とれますように。そして美味しいお味噌になりますように。
#大豆畑 #在来種 #自然栽培 #麦味噌 #沖醤油
昨日まで宮崎アートセンターで行われていた「わくわくWORK展」に足を運んでいただいた皆さま、ありがとうございました。
わたし自身こうした展示は初めてで、宮崎の素晴らしいデザイナーの方々の作品を見ることもでき、とてもいい刺激になりました。
客観的に自分の仕事一覧が見れたのもすごく良かった。
農業は10周年と思ったら、気がつけばデザイン業は25周年、くらい。大阪→東京→宮崎と場所を変えながら随分とたくさん作ってきたものです。
年を追うごとに考え方は少しずつ変わってきているけれど、大阪の頃から多分ずっとブレていないのは「クライアントの向こうにいるエンドユーザーをちゃんと見たい!」ということかなと。
実はそれが見たくてここくを始めたところもあるくらいです。
ここくのパッケージはいい紙を使ってるわけでもないし、凝った装飾をしているわけでもないので、デザインの賞なんて取れないです。
でも大事なのはそこじゃないし、もっと言えばデザインより味が一番大事なわけで、本当の「継続的な」評価はデザインではなかったりもして。
今は一から納得のいくものを作って届けることができているし、良くも悪くもしっかりエンドユーザーを見れているから、全て自分の中で腑に落ちていることを確認できました。
そんな感じで、デザイン→農業と180度転換したように見られがちですが、実は全部グラデーションで繋がっていたりします。
はて、こんな話がこのアカウントでどこまで通じるのか謎ですが(苦笑)、、やっぱりデザインの仕事も好きなんです。
ジャンルバラバラの発信で申し訳ないですが、今後もこんな感じでお送りしていきます^ ^
最後になりましたが、今回声をかけてくれた @risorarさんや委員の皆さん、準備から会期中のご面倒まで、色々と大変お世話になりました。貴重な機会を与えていただき、心より感謝申し上げます。
宮崎、まだまだいろんな可能性がありそうですね!
#デザインのお仕事展 #宮崎アートセンター #デザイン
子供の頃、下校時にこれをちぎっては友達に投げてくっつけて遊んでいた草。
くっつき虫、とか言ってたかな?調べたらコセンダンという名前だそうです。
耕作放棄地だった畑にはこれがたーくさん生えていて、トラクターで潰しても潰してもなかなか消えないのです。
よくよく観察していくと、ボロボロにされても土に埋められても途中で切られてもしっかり生きていて、なんなら切られたら切られただけ増えていくことが分かってきました。
これではキリがないので、今日は畑を歩いて回り、全部手で拾い上げました。
畦に生えたコセンダンも花真っ盛り。今のうちに刈っておかないと、あのトゲトゲがグローブや服について大変なことになります。
だいぶ涼しくなってきたので、年内あと一回草刈りすればいいぐらいかな?
来月の大豆の収穫を念頭に、畑の整備が続きます。
#コセンダン
あんみつ好きのみなさん、お待たせいたしました!発酵スイーツ研究所、10月の研究発表は「クリームあんみつ」です。
砂糖不使用のたまり餡あずきとふわふわ豆腐白玉、そして豆乳生クリーム。黒蜜は沖醤油とデーツシロップで作っています。
豆乳クリームのコクとたまり餡あずきの甘いハーモニー、そしてふわふわの豆腐白玉と寒天のぷりぷり食感。さらに塩茹で有機あずきと、贅沢にも沖醤油を使った黒蜜が旨みを引き立てます。
研究に研究を重ねてきた砂糖・乳・卵不使用の至極のあんみつ。この秋ぜひご堪能ください。
店舗で土日のみの受け取りになります。Webサイトからご予約の上ご来店くださいませ。
#発酵スイーツ研究所 #たまり餡 #砂糖不使用 #プラントベース #グルテンフリー #あんこ部 #清武町 #宮崎カフェ #宮崎観光