ウツギの花が咲く頃に大豆を撒きなさい。
地区に住む90歳のご老人にそう言われてこの花の名を覚えました。でも麻尻大豆をくれた高千穂のシンイチさんは7月20日前後と言います。その差は2ヶ月以上あるわけです。
5年やってみて分かってきましたが、これは梅雨が大きく関係しています。梅雨前にまくか、梅雨が終わってからまくか。麦との輪作の場合はどちらを選ぶかはかなり悩ましい。
大豆、麦、それぞれの収穫時期、成長の仕方、草の管理、どれを考えても一長一短。今年は片方を今月中に、もう片方を梅雨明けに蒔いてみようかと考えています。
なるほど。今年はもっと収穫して恩返し出来るように頑張ります。
今日のお昼時、神社の鳥居の階段で大股を開いて談笑していた大先輩2人と立ち話をしました。
ここは江戸時代の頃は馬を放牧していたそうです。字は「牧原(まきばる)」。見渡す限り人家もない、山だけのこの景色を、江戸時代の頃は馬がみていたのでしょうか。
今日もここで夕暮れを。
いつの間に、ひとりが寂しくなくなったのでしょう。
ひとりが寂しいと思えるのは幸せだからですね^_^
麻尻大豆がたくさん花を咲かせています。
この大豆はリビングマルチのために4月に蒔いた大豆。リビングマルチとは、畝と畝の間に敢えて草を生やし、影をつくることで草を生えなくするというものです。
大豆は成長が早く、葉が茂るのも早い、しかも土を肥やし、枯れた葉も土を覆うので本当に草を生やすことなくとても助かりました。
しかしどんどん大きくなるので2回ぐらい摘心。切っても切ってもめげずに伸び続け…こうして結局花をつけたのは結構驚きです。
適期に撒かないとツルばかりが伸びて花が咲かない、サヤがつかない「ツルボケ」状態になるのが常識。これはちょっと考えを改めなくてはいけない現象です。もしこれで収穫までできれば、畝の間でも草を抑制しながら栽培できるということ。
田んぼの畦に蒔いたと言われる畦豆は、もしかするとこの方式なのかもしれません。
じいちゃんばあちゃんがしている隣の畑。
この畑は草がほとんど生えなかった。雑草の種が風で飛んできて芽を出しても、2人は広い畑の中を1つずつ摘んで歩くから。
もう何十年とこんなことをしているから土に草の種が混じってない。びっくりするぐらい草が生えてこない。 …ところが昨年、さすがに体力的に厳しくなったのか畑を他所の誰かに貸した。
借りた人はニンニクを植えたまでは良かったけれど管理が全然されないから最後は草だらけに。収穫すらちゃんとせず半分くらい放置。
じいちゃんばあちゃんが「草を生やさんでくれんか」と頼むと、じゃあもう作らないと言われ、再び2人が管理することになった。
来る日も来る日もここにきて、一日中2人で草を抜いてる。今ようやく半分ぐらい。
取り残され、置き去りにされたニンニクは拾い集め、草は手で刈って倒し、乾いてから腰に結びつけた袋に入れ、ヨタヨタと畑の外へゆっくりゆっくり運んでいく。
もうきっと、草の種は随分土に混じってしまっただろう。何十年もしてきたことが一瞬のうちになくなってしまった。
悔しいとか悲しいとかではない。
これまで夫婦でしてきた静かな営みも、今毎日している目の前の作業も本当に儚い。それでもまた、静かに元の姿に戻そうとする2人のひたむきさに涙が出そうになった。
いつか、2人が来れなくなる日が来るだろう。後継者はいないから草だらけになるかもしれない。誰かが借りることになっても、その人はこの姿をきっと知らない。
今私が借りている畑にも、かつてこんな姿があったのだろうか。
@nene_dougu 石を拾ったりするのもそうなんです。ご先祖さまが大切にしてきたものを、次に使う子供達のために地道に石を拾っては畑の外に出します。そんな営みを知らない他所のひとが借りるということなんですね。
貸したがらない方の多い訳を、納得する思いがします。
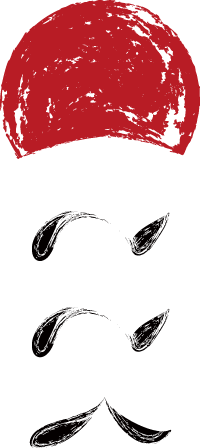










私の実家は、下関市の山と田んぼに囲まれた町です❗私の実家も農家で、私が子供の頃は掛け稲してました😊そして、自家栽培した大豆で、子供の頃は曾祖母と味噌なども作ってました🎵
はじめまして❗私は子供の頃、しいのみをフライパンで煎って食べてました😁インスタで知ったんですが、螢籠、私の実家の町でも作ってるみたいです🎵ぜひフォローさせてください❗